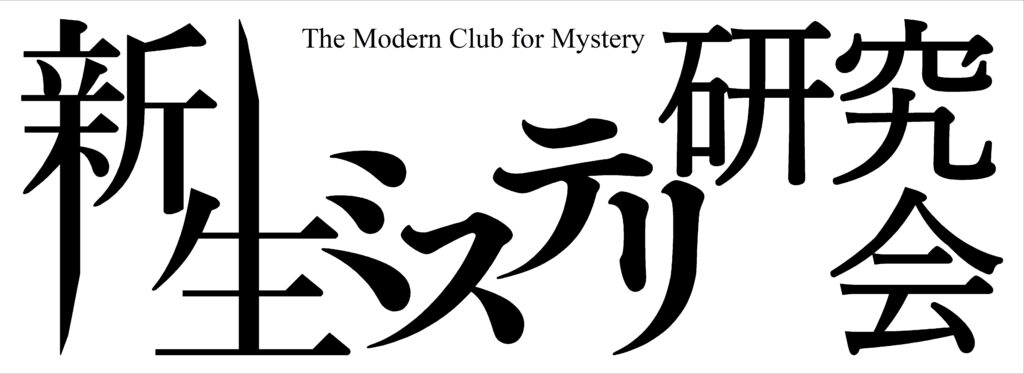
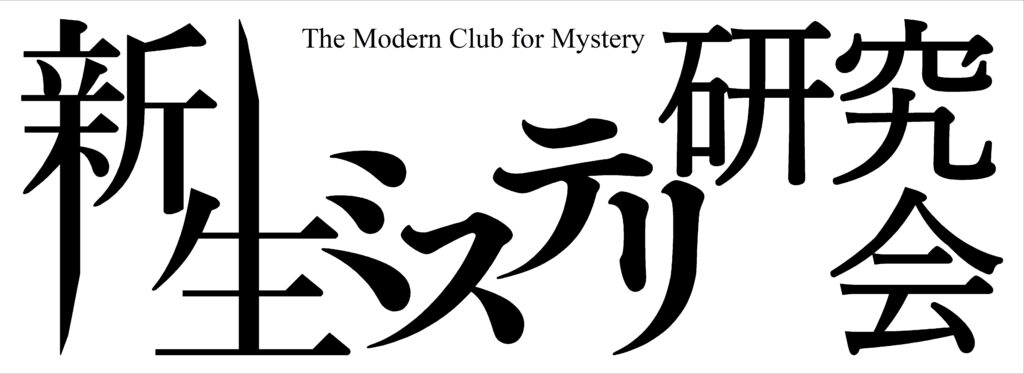
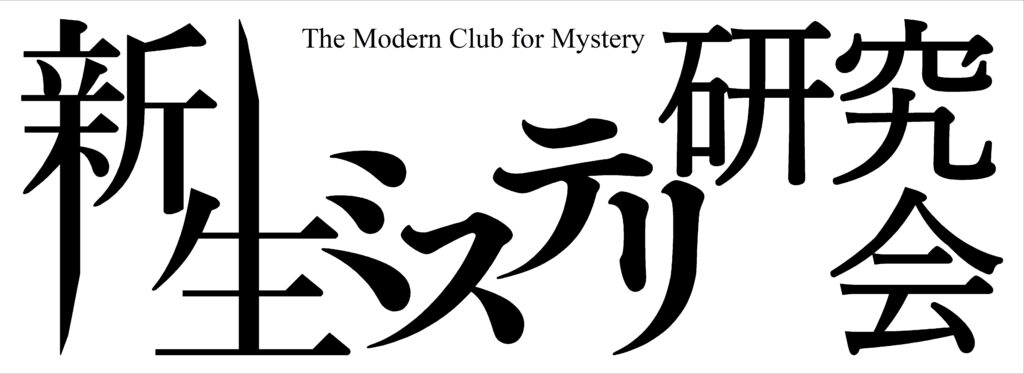
無料配布_一覧
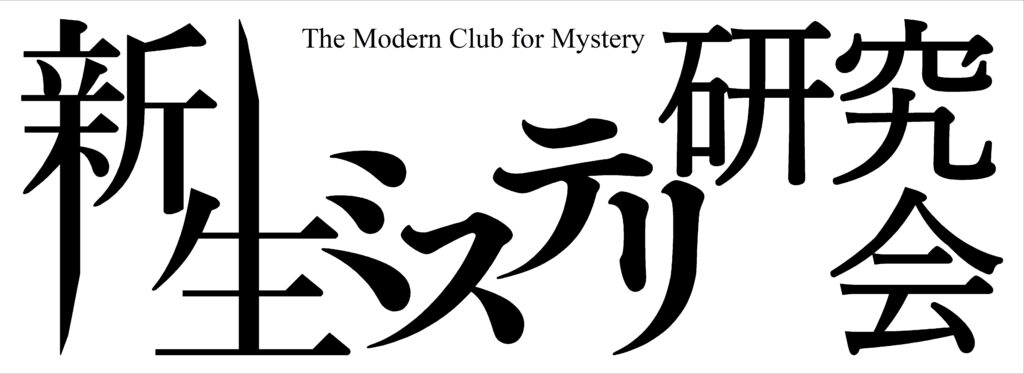
文学フリマ札幌10に参加します!
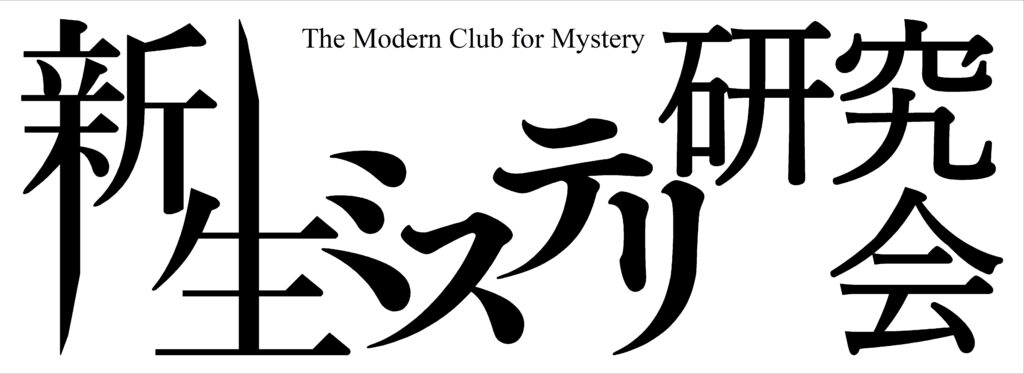
〝計画と実行の日〟への当てつけの具現です。
コロッケコメンテーターを目指している玄米が食べたいです、よろしくお願いします。
さて。
以前、本研究会の合作誌『MysteryFreaks vol.3』にて〝岩井環季の研究ノート1:準備〟と題して、わたしなりにミステリについてうだうだ考えたものを載せていただきました。その際、その国が育て上げたミステリ文化も知りたいよね、ってことも書きました。
他国の文化に触れるならば今は大阪・関西万博も条件を満たしていますが、人混み苦手なコミュ障には死地も同然。行きたくない。
ひょんなことから仕事関係でオランダに赴く機会がありまして。……まあ、これはオランダを標的に定めるしかないですよね。
そうだ、フィールドワークしよう。
フィールドワークとは、研究対象の現場を直接訪れて収集した情報や史料を分析する調査手法のこと。
「ミステリー」ではなく「ミステリ」と称したい菱川副会長のような感覚なのでしょうね、フィールドスタディなる呼びかたも存在するようです。
今回は地域調査として、文献・情報調査(インドアワーク)および現地調査(アウトドアワーク)に挑戦しました。見様見真似なので「挑戦」です。いつか「実施」できるようになりたいです。
なお、世間一般の認識がどうだか存じ上げませんが、後期クイーン的問題はミステリ創作系統におけるミュンヒハウゼンのトリレンマだの、ミステリ史は進化論の歴史と似てるだの、そのような理解をしている人間(わたし)の単独調査であるため正確性は保証できません!
単純に調査が追いついていない部分もありますが、とりあえず色眼鏡上等でよろしくお願いいたします☆
ということで、義務教育の知識に加えて在日オランダ大使館と在オランダ日本大使館のHPを張って「仲良しだよね」で済ませるのは不親切のような気がするので、もう少しまとめておきます。箇条書きで。
・The Netherlands/オランダ王国
・西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家、ベネルクスの1国
・国土面積36337平方キロメートル、人口およそ17600000人
・12の州で構成(北ホラント州Noord-Holland、南ホラント州Zuid-Holland、フローニンゲン州Groningen、ドレンテ州Drenthe、フリースラント州Friesland、オーファーアイセル州Overijssel、フレヴォラント州Flevoland、ユトレヒト州Utrecht、ヘルダーラント州Gelderland、北ブラバント州Noord-Brabant、ゼーラント州Zeeland、リンブルフ州Limburg)
・国歌Wilhelmus van Nassouwe
・首都アムステルダム(王宮・政府官庁はデン・ハーグ)
・とにかく鎖国していた日本と唯一国交を繋いでいた程度には、柔軟で寛容、革新的、国際的なお国柄
・これ以上は「オランダ 観光」で検索!!
他にも、ハイネケン社長誘拐事件だけでなくゴッホの耳切り事件と自殺、エラリー・クイーン『オランダ靴の秘密』に登場したオランダ靴、松本清張や有栖川有栖がそれぞれ作品の舞台にした1965年に日本人の他殺体が発見されたアムステルダムのヤコブ・ファン・レネップ運河……あれれー? 写真が無いぞー、どうしてかなー?
不思議なこともありますが、とにかく、調査方法としてフィールドワーク(とくに、地域調査。文献・情報調査および現地調査)に挑戦しました!!
まずはオランダの推理小説史に触れていきます。概論です。(まとめかたが不得手なので若干、時系列が前後します。一応かたじけないとは思ってます。)
なるべくたくさんお名前を書いておきます。何故って? 合ってる自信が無いからです。気になったら確認してくださいませ。
また、作品名に使う括弧は、日本で見慣れている『』を用いております。)
長くなるので先に挙げておきましょう。
他国事情を知らないのですが、
・短編集を飛び越えて長編推理小説が育てられた点
・探偵役の2大巨塔は、警察官&ジャーナリスト
・他分野で成功してから推理小説を描いた著作者が多い
オランダのミステリ文化の特徴はこのあたりだと思われます。
うーん、国民性……?
閑話休題。
流石オランダ、なんやかんや日本と仲良しでいらっしゃいます。
中島河太郎『日本探偵小説史』より、1861年に神田孝平(1830-1898)が『和蘭美政録』の内2編『楊牙児奇獄』、『青騎兵並右家族供吟味一件』として邦訳したオランダの推理小説が存在すると紹介されています。(修正20251229:2編の題名について、記載漏れしていました。すみません)
1821年にオランダで発表されたヤン・クリステマイヤ(Jan Bastiaan Christemeijer/1794-1872)が著した『Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafrecht en uit die der menschelijke misstappen.』のことだと思われます。中島氏に「本格的な構成はポーのモルグ街に譲らねばならない」と評されているものの、鎖国中によくもまあ来日してくださいました。長旅おつかれさまです。
(個人的に、推理小説とされた『和蘭美政録』の2編に史実との関連が無いか気になり、当時の資料を漁ろうとしております。見つからなくて楽しくなってまいりました。)
ということで、1841年ポーによる『モルグ街の殺人』が発表され、推理小説(探偵小説)が黎明を迎えまして。
まもなく、コリンズやガボリオ、ディケンズらを経てドイルによるシャーロック・ホームズの創造を迎えて推理小説の文化が諸外国を巻きこみながら醸成されていくことになります。
オランダも例外ではなく、国内出版社は次々に外国作品を蘭訳します。
そしてまもなく、英語圏で作家として活躍していたマールテン・マールセン(筆名Maarten Maartens/本名Jozua van der Poorten Schwarz/1858-1915)によってイギリスの出版社から1889年『The Black Box Murder』、1899年『The Sin of Joost Avelingh』が発表されます。が、オランダ国内では推理小説への軽蔑的な認識や短編小説への無関心存在していたようで。1900年前後にスリラーブームが到来するものの、まもなく収束。(オランダでは推理小説はスリラーに含有されている印象)
結局、マールセンを起点とした推理小説文化の発展は見送られてしまいます。(日本でも純国産ミステリの誕生は遅れをとりましたが、オランダとは条件が異なるご様子)
とはいえ地理的に翻訳作品は流入しやすく、1917年にようやくオランダ探偵小説の創始者と謳われるイファンス(IVANS (= I = J) – VAN -S/Jakob van Schevichaven/1866-1935)がイギリスを舞台とした『De Man uit Frankrijk』を発表し、以降GGシリーズにてシャーロックホームズを彷彿とさせるイギリス人名探偵Geoffrey Gill&オランダ人弁護士Willy Hendriksを活躍させ始めました。(ドイルがワトソン博士を医者にしたように、イファンスもヘンドリクスさんを弁護士にしたかったのかもしれない)
そんなこんなで1920年代に……そう、推理小説の古典黄金期が訪れますね!
イファンスは相変わらず継続してGGシリーズのほかメイ・オーニル(May O’Neill)のメイ・シリーズやヘラルド・ファン・パンフイス(Gerard van Panhuis)のDennenbergシリーズ(Dennenbergは架空の地名?)など他の人物を主人公に据えて、推理小説の執筆を継続します。彼の牽引に伴い、劇作家ヘルマン・ハイエルマンス(Herman Heijermans/1864-1924)による『De Moord in de Trein uitkwam』の発表をはじめとして作家・法律家ベンノ・ストクヴィス(Benno Jules Stokvis/1901-1977)、作家・演出家オーガスト・デフレスネ(Marie André Antoine August Defresne/1893-1961)、雑誌編集者ベン・ファン・アイセルシュタイン(Bernard van Eysselsteijn/1898-1973)、ヤン・アポン(Johannes Adrianus (Jan) Apon/別の筆名Max Dupont/1910-1969)、ハンス・ペナーツ(本名Hans Pennarts/筆名Koerts Hugo/1903-1976)のように追随者は存在しました。
イファンスが晩年を迎えたころ、英米ではスパイや私立探偵などのサブジャンルが開拓されているころ、オランダでは再びスリラーブームが到来します。
ウィリー・コルサリ(Willy Corsari/Wilhelmina Angela Schmidt/1897-1998)は1931年『De Onbekende Medespeler』を発表してルンド警部(Inspecteur Lund)シリーズの短編パズルミステリを継続させたり、『Dr. Vlimmen』三部作で有名なA.M.H. Roothaert(アントン・ルートハールト/Antonius Martinus Henricus (Anton) Roothaert/1896-1967)は1933年から1935年に『Spionage in het Veldleger』をはじまりとしてアムステルダム警察のエバート・ピロン(Evert Piron)を主人公とした4作の推理小説を1発表したり、後のベストセラー作家ヤン・デ・ハルトグ(本名Jan de Hartog/筆名F.R. Eckmar/1914-2002)によるヴィーベ・ポエジエ(Wiebe Poesiat)とグレゴール・ボヤルスキー警部(Gregor Boyarski)が活躍する作品などが発表され続けたことで、次第に「警察」が小説に浸透してきていきました。
イファンスが亡くなった1935年には、ブルーナ社(A.W. Bruna Uitgevers/Uitgeverij A.W. Bruna & Zoon)に『Het mysterie van St. Eustache』が持ち込まれ、出版されます。文筆家アントン・ファン・ダインケルケンの提案からイファンスと同様に本名のイニシャルから筆名を作成したハファンク(HAVANK (H.VAN.K.)/Hendrikus Frederikus van der Kallen/1904-1964)は、フランス警察の警部ブルーノ・シルヴェール(Bruno Silvère)と助手のシャルルC.M.カルリエ(通称・影Schaduw)を擁するシリーズとともにイファンスの後継者として執筆活動を重ねていきます。(シリーズ9作目にあたる1939年『Hoofden op hol』からはカルリエが主役を引き継いでシルヴェールシリーズからシャドウシリーズに変更されます。)
時代に翻弄されて、1945年に第二次世界大戦の末期を迎えると、ナチス独裁政権下にあった諸国の解放を進めていくアメリカ軍への配布を目的としたペーパーバックが登場します。ポケットに入る小型かつ安価なペーパーバック(ポケットブック/パルプマガジン)はオランダ国内でも普及していきました。
解放後は、J.F.クリフイス(Jan Frits Kliphuis/1916-1972)による1945年『Recht zonder Wet』、マルテン・ファン・アラント(筆名Marten van Allandt/本名Pieter Mello Heil/1920-2003)による1946年『Misdaad in Mei』、1951年に誕生した姉妹コンビ作家マーティン・モンス(筆名Martin Mons/本名Margrete Anna Wierdels-Monsma&Hildegard Saskia Monsma/1892-1964&1906-1964)が創造した警察官ペルキン(Perquin)を主人公とした作品を継続的に発表します。他方、40年代から50年代前半にかけてフェンロー事件からメーヘレン事件まで幅広い種類の事件が跋扈していたものの創作にはなかなか反映されず、戦前と類似する内容が続いていました。(当時から知名度が高いうえに内容も興味深い、創作者には垂涎の題材でしょうに……)
混乱が落ち着いてきた1950年には、20世紀初頭、1930年に続く3度目のスリラーブームが到来しました。
リコ・ブルトフィス(Rico Bulthuis/1911-2009)は、1950年『De misdaad van Richard Ross』からはじまったポール・ピケ警部(inspecteur Paul Piquet)の創造だけでなく、ラジオドラマ『Daiyamondo (Diamanten)』は日本語のみで限定出版された。(Burutuhauso Riko名義/詳細確認中)
また、1947年から開催されていたブルーナ社による新人探偵作家発掘コンテストwerd in de detectiveprijsvraag van Bruna(関連調査中:prijsvraag voor misdaadverhalen)も手伝って、多くの若手推理作家が誕生しました。
1952年にはジャーナリストのヨープ・ファン・デン・ブローク(Johannes Frederik (Joop) van den Broek/別の筆名Jan van Gent/1926–1997) が『Parels voor Nadra』で最優秀賞を受賞&1953年に同作を出版しました。以降、オランダ初ハードボイルド作家として活躍していくブロークが創造した主人公であるジャーナリストのレックス・ファン・デル・トゥイン・ワレマ(Lex van der Tuyn Walema)は、はじめてオランダ推理小説の主人公が「警察」から離れました。
推理小説が誕生してミステリ文化の醸成初期を迎えたころは諸国の近代的な警察組織の設立が重なりますので、犯罪と戦う登場人物として警察が選択されるのは想像に易しいでしょう。まもなく諸外国では〝探偵〟が推理小説を席巻しましたが、オランダでは定着せずに警察のほか、探偵に代わる〝ジャーナリスト〟が同様の役割として活躍していきます。
もちろん〝ジャーナリスト〟が活躍し始めても〝警察〟の勢いは衰えず、1953年に作家デビューしたW・H・ファン・エームラント(W.H. van Eemlandt、本名:Willem Hendrik Haasse、1889-1955)は、アムステルダム司法警察のアールト・ファン・ハウトヘム警視(Aart van Houthem)を主人公とするシリーズを3年間で12作発表しました。(逝去によって未完となった2作は、ひとつは彼の娘が、ひとつはブロークがそれぞれ完成させて発表されています。)
膨大な作品を著した作家アブ・ウィッサー(Albert (Ab) Visser/1913-1982)のように推理小説の執筆と研究を両立する人物も現れる一方、ハファンクは年に数作シャドウシリーズ(‘Schaduwen’)を発表しながら、1955年以降ブルーナ社が立ち上げてペーパーバックの装丁をディック・ブルーナが務めた黒熊シリーズ(Zwarte Beertjes)から諸外国の推理小説を翻訳して巨匠としての地位を確立していました。
また、1950年代は複数の教授がそれぞれペンネームを用いて探偵小説を描き上げました。歴史学者プレッサー教授(Jacob(Jacques)Presser/1899-1970)はハギ・M・ライス(Haggi M. Reis)、ファン・デル・ヴァル教授(Libbe Gerrit van der Wal/1901-1973)はチャリング・ディックス(Tjalling Dix)、ファン・デン・ベルク教授(本名Lodewijk Paulina (Lode) Van Den Bergh /1920-2020)はアスター・ベルコフ(Aster Berkhoff/後述)を用いました。(とくにファン・デル・ベルク教授は戦時中から警察小説を執筆していましたが、1950年以降はマーカス警部(inspecteur Marcus)を主人公に据えて本格的に執筆活動をしました。)
国際的ハンドブックに名前が載っているオランダ人3名はいずれも英語で作品を執筆しており、内2名――ジョシュア・ファン・デル・ポルテン・シュヴァルツ(Jozua van der Poorten Schwarz/前述したマールテン・マールセンのこと/1858-1915)、ロバート・ファン・ヒューリック(Robert Hans van Gulik/1910-1967)、ヤンウィレム・ウェテリンク(Janwillem van de Wetering/1931-2008)のうち後者2名――中国や日本への関心があったファン・ヒューリックとウェテリンクは、このころ、それぞれティ判事(Rechter Tie-verhalen/ハヤカワ・ミステリにて〈ディー判事シリーズ〉として和爾桃子(訳)が存在している!!)やサイトウ警部(Japanse politieman Saito)を主人公とした作品を発表しました。
とくに、ファン・ヒューリックは江戸川乱歩との交流があり、日本国内の雑誌にも登場しています。(雑誌『宝石』1950年9月号にて、グーリックと表記されているがファン・ヒューリックのことを指している。乱歩から接触を図った模様)
その後、江戸川乱歩はファン・ヒューリックを通じてW.G.キエルドルフ(=ピム・ホルドルプ/以下、記述)とも文通したご様子(詳細調査中)です。
なお、1959年にはピム・ホルドルプ(筆名Pim Hofdorp/本名Wilhelm Gustave Kierdorff/1912-1984)は、ハーグ推理シリーズ(Haagse Mysterie Reeks/その後Nieuwe Haagse Mysterie Reeks)を立ち上げて、ファン・アレンベルク警部(van Aremberg)を主人公とした『Katastrofe in Kijkduin』、『Vampiers van Valkenbos』を発表、巻頭に地図を挿入する試みを成功させました。まもなくコル・ドクテル(Cor Docter/本名Cornelis Docter/筆名Francis Hobart、Salem Pinto、Sidney Spring、Mieke Brandt、Ted van Galen、Carolus Kassandra、Tonny Leenders、Ria van Rooijen、Gitta de Regt/1925-2006)もオランダを舞台として警察長官ダーン・フィッセリン(Daan Vissering)を主人公とした『Moord aan de Maas』を契機としてシリーズを継続させます。
1960年代になると、諜報員やスパイの揺籃地となったオランダでは英国諜報員ジェームズ・ボンドの圧倒的な活躍に引きずられて、ヤン・ルーウェン(Jan Louwen/筆名Ted Viking/1924-2000)が1964年から諜報員マクレガー(McGregor)を主人公とした多くのスパイ小説を、ヘンク・ウールベッキング(Hendrik-Jan (Henk) Oolbekkink/1931-2012)によって1966年から諜報員グロッツ(Glotz)と元飛行士ティム・スペンダー(Tim Spender)を主人公にした作品を発表し、その後まもなく、ゲルベン・ヘリンガ(Gerben Wytzes Hellinga/1937-2024)がより洗練させてシド・ステファン(Sid Stefan)を主人公に据えて『Dollars, Messen, Vlammen』を第1作としたシリーズで成功を収めました。
半ばには、アッピー・バーンチャル(Albert Cornelis(Appie) Baantje/1923-2010)『De Cock en een strop voor Bobby』から立ち上げた年配の警察官デ・コック(Jurjen De Cock)と若手警察官ヴレッダー(Vledder)が活躍するデ・コック(De Cock)シリーズによって次第に人気を獲得していき、1歩ずつハファンク以来の国民的推理作家への道を上っていきます。
ハファンクの逝去を経て、ピーテル・テルプストラ(オランダ語Pieter Terpstra、フリジア語Piter Terpstra/Piet Grilk、Peter Torenvliet、Terpstra/1919-2006)は、Havank&Terpstra(Havank+Terpstra)の筆名を用いて1965年『De erven Mateor』を発表し、以降も同筆名でハファンクの遺作を引き継いでいきました。
リヌス・フェルディナンドゥッセ(Rinus Ferdinandusse/1931-2022)は、1966年『Naked over the Fence』からジャーナリストのルガー・レミング(Ruger Lemming)を主人公としたシリーズのほか、別の筆名であるマルテン・トレファー(Marten Treffer)を用いてアムステルダムを舞台とした警察小説を発表しました。
風変わりな警察官フロリス・ヤンセン(Floris Jansen)を創造したトン・フェルフォールト(Ton Vervoort/翻訳者としてはペーター・フェルステゲンPeter Verstegen/1938-) によって1967年(1968年?)には『De Zaak Stevens』が発表されました。(ドシエ形式(’dossiervorm’)と呼ばれる、製本された調査報告書や再現された証拠品の数々は、現代の日本のリアル脱出ゲームのキットと似てる印象。)
また、このころからブームを後押しするために6月をスリラー月間(Month of the thriller)として、書籍購入者全員に短編小説が配布されるなど、作家の創作意欲を書きたてる作戦を実施していた。
その後、1971年を機にウールベッキングとフェルディナンドゥッセが引退を宣言し、推理小説の出版数が激減しますが、1975年には前述したヤンウィレム・ウェテリンク(Janwillem van de Wetering)は英語およびオランダ語で『Het lijk in de Haarlemmer Houttuinen』を発表しました。グリープストラ警部(Henk Grijpstra)とデ・ギア巡査部長(Rinus de Gier)のコンビを創造したウェテリンクは、国外(とくにアメリカ)での収入が保障されていたり作家としての知名度向上に努めていたりしたことでオランダ推理小説において確固たる地位を築きました。同じく1975年にジャッキー・ローレンス(Jackie Lourens/Adriana Luberta Klasina Lourens-Koop/1920-2000)は『Ze kunnen het niet laten』を発表し、堅実に推理小説を発表していきました。このふたりを筆頭に支えられた推理小説は、1970年末以降、国外からの翻訳作品やテレビ推理小説シリーズの流入に伴い、急速に人気を得ていきました。
1980年代には、ファン・ゾメレン(Peter Jacob (Koos) van Zomeren/1946-)は、1981年に『Haagse lente』を発表してから1981『Minister achter tralies』、1982『De hangende man』、計3作の推理小説を発表すると元のジャンルへ帰って行ってしまったが、テオ・カペル(Theo Capel/1944-)は『Spoiled Money』を、ジャック・ポスト(Jacques Post/1951-)は『Leer om leer』を、SF作家フェリクス・テッセン(Felix Thijssen/1931-)は『Wildschut』を、トーマス・ロス(Tomas Ross/Willem Hogendoorn/1944-)は『De honden van het verraad』を発表します。同時期にはフリー・ネーデルラント誌(Vrij Nederland)の年間誌『VN’s Thriller & Detectivegids』、専門誌『Thrillers & Detectives』が創刊され、一度は引退したと思われたヘリンガ、ウィリー・コルサリ、フェルディナンドゥッセ、ファン・デル・ブルークも沈黙を破って作品を発表していきました。
また、国内に記念碑や肖像画が飾られていたり公園や橋の名前の由来になったり、亡くなってからも国内人気が高いハファンクに寄せて1984年にはブルーナ社によってハファンク没後20年に際してDe Havank-trofeeが開催された。
とくに、トーマス・ロス(前述)は1986年にオランダ推理作家協会(GNM:Genoostschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs)創設に貢献し、ヨープ・ファン・デン・ブロークの1982年『De gouden strop』を由来としたDe Gouden Strop(黄金の首吊り輪賞/金の投げ縄賞/オランダ推理作家協会賞)を立ち上げて年間最優秀推理小説を称賛する環境を整えました。
ティム・クラベーによる1992年『失踪』が翌年スウェーデン推理作家アカデミー最優秀翻訳ミステリー賞受賞など、創設以来の受賞作は他国で高い評価を受ける作品も少なくありません。
(確認中:前身はハヴァンク賞?→グーテン・ストロップ賞?/1993-2001にはBruna Gouden Strop賞)
(余談:オランダ警察が1989年から運用する指紋認証システムHAVANK(Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie)と名前が似てる……これは偶然ではないと信じたい。)
この隆盛の中で、1987年に会計士ボブ・メンデス(筆名Bob Mendes/本名David Mendes/1928-2021)が『Dag van schaamte』から自らファクションスリラー(フィクションと事実を混ぜ合わせたスリラー/’faction-thriller’)と称したジャンルを多数の著作とともに開拓していったりヤコブ・ウィス(Jacob Vis/1940-)による実在都市アイセルモンデ(Ijsselmonde)を舞台にした警察小説である『Prins Desi』でDe Gouden Stropを受賞したりした他、アッシュ・スティル(Ashe Stil/1953-)はオランダ黄金時代とされる17世紀を舞台としてアムステルダムの水道執行官(water-bailiff/waterschout)であるウィレム・ルートマン(Willem Lootsman)を探偵役に据えたシリーズを、ジャーナリスト兼作家マルティン・クーメン(Martin Koomen/1939-)は第二次世界大戦に活躍する諜報員ロバート・ポーランド(Robert Portland)を主人公としたシリーズをそれぞれ発足させたり、1991年にスリラーの巨匠である言語学者ルネ・アペル(René Appel/1945-)による『De derde persoon』、1992年にクリス・リッペン(Chris Rippen/1940-)は『Playback』がDe Gouden Strop受賞を果たしました。
1991年にはボブ・メンデス(前述)の尽力によってオランダ推理作家協会(GNM)の姉妹団体フランドル推理作家協会(GVM:Genoostschap van Vlaamse Misdaadauteurs)が創設されます。
ボブ・メンデスが『De kracht van het vuur』によって2度目のDe Gouden Strop受賞を達成した1997年には、オランダ推理作家協会(GNM)はハファンク作品に登場するシャルルC.M.カルリエが由来である年間最優秀新人賞としてDe Schaduw(シャドウ賞)を設立し、オランダまたはフランドル出身の作家による処女作へ贈られるようになりました。
翌年の1998年には、フランドル地方の推理作家を支援することを目的としてジャーナリストのフレッド・ブラックマン(Fred Braeckman/1944-2015)がエルキュール・ポアロ賞(De Hercule Poirot prijs)を設立してフランドル地方における年間最優秀推理小説を称える環境を用意しました。(主催:tijdschrift Knack/開催:Antwerpse Boekenbeurs→boekenbeurs Boektopia in Kortrijk)
エンターテインメント小説を得意とするピーター・デ・ズワーン(Peter de Zwaan/1944-)が『Het alibibureau』によってDe Gouden Strop賞を獲得した2000年には、ヤン・ローゼンダール(Johannes Cornelis (Jan.C) Roosendaal/1921-2017)が中心となってベルト・ウィイスエ(Bert Vuijsje/Albert (Bert) Vuijsje/1942-)、 クリス・リッペン(Chris Rippen/1940-)とともに著した『Moorden met woorden』によってオランダのミステリ史が纏められました。
1995年『Dump』とともにデビューしたチャールズ・デン・テックス(Charles den Tex/1953-)が『Chance in hell』でDe Gouden Strop賞を勝ち取った2002年には、推理小説に関する情報が纏められたサイトであるクライムゾーン(Crimezone/www.crimezone.nl)が運営を開始し、読者投票によってオランダ語作品部門/翻訳部門/新人部門の作品を選出するクライムゾーン賞(前身:De Zilveren Vingerafdruk)が立ち上げられました。
同年、フランドル推理作家協会(GVM)は、国際推理作家協会(AIEP-IACW)の提案をうけたボブ・メンデス(前述)の声でDe Diamanten Kogel werd(ダイヤモンドの弾丸賞)を創設し、フランドル地方における年間最優秀推理小説を称える環境を整えます。
(名声>賞金/日本の鮎川哲也賞のようなイメージ)
シモネ・ファン・デル・フルフト(Simone van der Vlugt/1966-)が彼女にとって初めての推理小説である『De Reünie』を発表した2004年の前年(=2003年)には、オランダ推理作家協会(GNM)はDe GNM Meesterprijs(GNMマスター賞/GNM巨匠賞)を設立し、長年にわたりオランダ語推理小説というジャンルに揺るぎない貢献を果たした作家あるいはオランダ語圏における推理小説ジャンルの発展に大きく貢献した作家を表彰することにしました。
このころオランダミステリ史において巨匠の存在が認識されてきたということなのか、2007年には前述のエルキュール・ポアロ賞の姉妹賞のようなDe Hercule Poirot Oeuvreprijs(エルキュール・ポアロ生涯功労賞)がジェフ・ヘラールツ(Jozef Adriaan Anna Geeraerts/1930-2015)に授与されました。
2008年にはブルーナ社が創設140年を迎えた記念として、トーマス・ロス(前述)がハファンク・ロス名義でシャドウシリーズの続編を執筆し、以降、ハファンク・ロスを用いてシャドウシリーズ数作が上梓されています。
なんやかんやあってフランドル推理作家協会(GVM)が2011年に解散すると、2013年に創設されたフランドル推理作家協会(VVMA:Vereniging Vlaamse Misdaadauteurs)に、De Diamanten Kogel werd(ダイヤモンドの弾丸賞)運営をはじめとした一部活動が引き継がれます。
2019年、このような変遷を経たオランダミステリ史は、ペトルス・J.A.ヴィンケルス(Petrus Johannes Antonius Winkels/1954-2021)、ヨス・ファン・カン(Jos van Cann/1954-)に『Moord in het bronsgroen eikenhout』として1冊に纏められました。
さて。
オランダミステリ史概論はこのあたりで締めさせていただきます。
承知しておりますよ、「近年はどうなんだい?」って話ですよね。今までの流れを知らないとつまらないと思いましたもので、先に歴史を扱わせていただきました。
ひとまず参考として直近5年における、De gouden strop、De Schaduwprijs、De Hercule Poirot prijs、De GNM Meesterprijs、De Hercule Poirot Oeuvreprijs、De Diamanten Kogel werdにおけるそれぞれ受賞作品および作家(巨匠へ贈られる賞は歴代受賞者)について記載しておきます。
邦訳無し&まだすべて読めていないものでして。勧めるのが難しいのですが、ご関心がありましたら是非!!
・De gouden strop
2025年:『De prijs』(Marcel van de Ven&Willem Asman)
2024年:『De duiker』(Mathijs Deen)
2023年:『Musserts Schaduw』(John Kuipers)
2022年:『Vogeleiland』(Marion Pauw)
2021年:『Bloedsteen』(Bernice Berkleef)
・De Schaduwprijs
2025年:受賞者無し
2024年:レックス・ノートブーム(Lex Noteboom/1987-)『De Man met Duizend Gezichten』
2023年:受賞者無し
2022年:バス・ハーン(Bas Haan/Bas Jacob Joseph (Bas) Haan/1973-)『Lenoir』
2021年:フロリス・クライネ(Floris Kleijne/1970-)『Klaverblad』
・De Hercule Poirot prijs
2025年:未発表
2024年:『De prijs van de twijfel』(ジョー・クレス/Jo Claes/1955-)
2023年:『Het Buchinsky Incident』(ベニー・ボーデュワインズ/Benny Baudewyns/1958-)
2022年:『Joséphine』(アン・ロール・ファン・ニア/Anne-Laure Van Neer/1975-)
2021年:『Nachtstad』(ウーター・デヘアーズ/Wouter Dehairs/1981-)
・De GNM Meesterprijs
2018年:トーマス・ロス(Tomas Ross/前述)
2013年:ジャーナリスト兼翻訳家サスキア・ノールト(Saskia Noort/1967-)
2003年:アッピー・バーンチャル(Appie Baantjer/前述)
・De Hercule Poirot Oeuvreprijs
2024年:パトリック・コンラッド(Patrick Conrad/1945-/映画監督としても著名)
2013年:アスター・ベルコフ(Aster Berkhof/1920-2020/前述のとおり、長く推理小説を執筆してきた)
2010年:ピーター・アスペ(Pierre Aspe(Pierre Aspeslag)/1953-2921/Inspector Pieter Van Inシリーズが有名)
2007年:ジェフ・ヘラールツ(Jozef Adriaan Anna Geeraerts/1930-2015/ジャーナリスト、作家として活躍)
・De Diamanten Kogel werd
2016年:『Bling Bling』(ヤン・ファン・デル・クライス/Jan Van der Cruysse/1960-)
2015年:『Smeergeld』(ナウシカ・マーべ/Nausicaa Marbe/1963-)
2014年:『De Zwarte Duivel』(ヤコブ・ウィス/Jacob Vis/前述)
2013年:『2017』(ルディ・ソエテウェイ/Rudy Soetewey/1955-)
2012年:『Blauw goud』(アルマー・オッテン/Almar Otten/1964-)
うん。
他分野で活躍しつつ推理小説を執筆するスタイルはもはや伝統ですね。
これがオランダらしさなのでしょう。
よし、ようやくハイライトです、こんにちは。
せっかく現地調査(アウトドアワーク)ができる環境なのでね。とりあえず、可能なかぎり現地の方々に話しかけました!
ご安心を。暗闇を電気でねじ伏せた先人に倣って、人間なのでコミュ障をねじ伏せました。
さすが子供に優しいお国柄。アジア系の年齢がわからない彼らのおかげで、遅い送迎を心配されつつも、野生の人間とそれなりに話せました。急ごしらえのオランダ語習得になってしまったため心配でしたが、英語も十二分通じました。
また、きちんと集計しておりませんが、野生の人間を捕らえる打率は図書館が好成績でした。オランダの図書館の性質ゆえでしょうね。ありがとうございます、なんか、そういう図書館の構想(コペンハーゲン大学A new model for the public library in the knowledge and experience society)!!
それぞれ1週間を目安に狩場は変えましたが、時間の差異はあれども、いずれの図書館でも数時間に数名ほど話す時間を取ってくださいました。わたしの体力が持てはばもうちょい聞けただろうに、悔やまれますね。筋トレしよう、そうしよう。
〇知っている探偵役、警察官を3名あげてほしい(列挙)
〇ミステリ用語、教えてください!
上記2点は可能なかぎり聞くようにはしましたが、雑談形式だったので本当に雑談しただけの方もいらっしゃいます。
とりあえず、今回のテーマに基づいた調査結果は以下のとおりです。
〇知っている探偵役、警察官を3名あげてほしい(列挙)
シャーロック・ホームズ、エルキュール・ポアロ、マーティン・フィンチ、シャドウ(カルリエ)、デ・コック、カール・マーク刑事(特捜部Q)、ヨーナ・リンナ警部、リーゼ・メールハウト警視、ヴァランダー刑事、ダニエル・ホーソーン、エラリー・クイーン、ミス・ジェーン・マープル、オスロ警察殺人捜査課特別班、国家犯罪捜査局元長官ラーシュ(邦訳『許されざる者』)、コロンボ、86分署、リンカーン・ライム、モース警部、ラングドン教授、メグレ警部、シド・ステファン、エリカ&パトリックシリーズ、警察官スヴェン(Hallandsvitenシリーズ)、、金田一耕助、湯川学、アリーナ・コーンウォール(『海岸の女たち』)、ミカエル・ブルムクヴィスト(ミレニアムシリーズ)、マヤ・ノルベリ(マリア・ノーバーグ/『Störst av allt 』)、マルティン・ベック
人数も集計していましたが文字同士が重なりすぎて解読不能。これぞ視葭クオリティ、見ないで書くからですね。
これの他の反省として、事前調査で確認していたものの、オランダの推理小説史では「私立探偵」よりも「ジャーナリスト」「警察官」のほうがより浸透している実態を理解しきれていなかったため調査当初は質問に「探偵detectiefje」を用いていました。「探偵……」となった方に「事件を解決する人を知りたい」と補足したところ「警察官でも良いの?」と言われて「もちろんです」となりました。
最終的には57名が協力してくださり、回答総数は171でした。
ホームズ先生、ポアロ先生は精勤賞でした。仮に出てこなくても「〇〇は聞いたことある?」と尋ねれば肯定が返されましたので、さすがです先生方。
それから、翻訳ミステリ、殊に北欧ミステリの登場人物の名前がよくあげられました。強いですね、北欧。
オランダ出身の探偵役も打率が高めで安心しました。3人以上知っている方の多くは有名順を意識してくださったようで、ホームズ、ポアロなど世界的に有名な探偵役を優先してあげてくださったご様子で他の人物を聞いてみると2000年以降の作品を中心として登場人物の名前が多く上げていただけました。事前に「創作物の探偵役とか警察官は大方知ってるよ!」と大口を叩いておいたものの、当然知らない方々の名前は少なくありませんでしたし、無意識的にインタビュアーが日本人であることを意識させた可能性はあります。むずいのな、対人って。
その中でも、抜群にやべぇ人がひとりいらっしゃいました。わたしが日本から来たと伝えたことで日本人(金田一耕助、湯川学)捻りだしてもらえた可能性は低くありません。それでもさすがに激熱展開でした。彼がただのミステリ好きの可能性も大きいですが、世界の横溝正史、世界の東野圭吾を感じましたね……ノーベル賞とか『本陣殺人事件』とかの話で盛り上がってくれたあのおじ様、元気かな。
当然といえば当然ですが、推理小説に関する団体や愛好家を狙って捕獲していたわけではありませんので、お話ししてくださった方々の中には推理小説への関心が薄い方もいらっしゃいました。そのうちのひとりにはエルキュール・ポアロをフランス人だと思っている方がいらっしゃいました。お時間を取っていただいたお礼を告げた後に呼び止めて「最後にひとつ……エルキュール・ポアロはフランドル出身ですよ」と伝えたときの表情、最高でした。同様の読書遍歴の方は日本にも探せばいらっしゃるかもしれませんね。(日本で現地調査するポテンシャル、わたしにはございません☆)
〇ミステリ用語、教えてください!
オランダの文献で独自の用語がなかなか見つけられなかったもので。諦めて本職の人間に聞いてみました。
心当たりが無い方が多いご様子で、基本的に英語圏と同じものか直訳が用いられていました。
〇職業当てゲーム/図書館へ来た目的当てゲーム
用意していた最初の設問「知っている探偵役、警察官を3名あげてほしい(列挙)」にてシャーロック・ホームズを挙げてくださった学生さんを相手に試してみたらウケが良かったため、以降から時間があれば実施しました。やはり楽しいことに乗ってくださるのは全世界共通です。
こんなところでしょうかね。うん、稚拙なうえに長い。申し訳ない。かたじけないっす。
さあ、纏めに掛かりましょう。
一般的に推理小説といえば、英米仏、北欧が強いイメージが存在し、オランダはいずれの国々とも近いですよね。
世界には7000ほどの言語が存在しており、語族(=起源が同じだと学問的に証明できる諸言語)から考えてみると、イタリック語族に含まれるラテン語からロマンス諸語と呼ばれるイタリア語、スペイン語、フランス語が派生しており、ゲルマン語族は北欧や英語が含まれています。ちなみに、オランダ語もゲルマン語族でいらっしゃいます。
地理的にも歴史的にも語族的にも、ミステリ文化の醸成には困らない条件が揃っている印象です。
他方、オランダミステリ史概論として書かせていただいたように、ミステリ文化醸成まで長い時間をかけています。
1840年代から新聞小説(ロマン・フィユトンroman feuillton)が隆盛を迎えたフランスのように短編小説が親しまれる環境が既に存在していたわけではないのかも(過去の新聞について、詳細調査中)しれませんが、国内に短編小説やオムニバスへの忌避があったという記述の他には――推理小説(犯罪小説)に対する偏見や軽蔑が根底にあった、推理小説は認知度が低く不人気で売れない、別分野で成功した作家が息抜きに書いてみる分野――このような20世紀から活躍する国内推理作家がよく自虐に用いていた内容を参考にすると、だいぶ険しい道のりだったのでしょう。
これはオランダ文学の有識者に確認したいところですが、オランダ国内でオランダ人が謎を解く形式が珍しいようにも感じました。ハーグ推理シリーズを立ち上げたピム・ホルドルプが画期的なことをしたように見えます。(*氏は画期的なことをなさっています)
ということで、教えてください有識者さん。
たとえば日本では翻訳ミステリが広まって江戸川乱歩による明智小五郎が活躍する第1作『D坂の殺人』が1925年に発表されました。諸外国(特にヨーロッパ圏)と比較すると国産ミステリに遅れが見えるものの、以降、〝推理小説家〟〝探偵〟は定着していきます。多方、マールテン・マールセンによる1889年『The Black Box Murder』、イファンスによるGGシリーズ開始が1917年ですが、結局オランダでは定着せず時が過ぎました。
1950年代に作品数の増加に伴い多様性がもたらされたころ探偵の代わりに〝ジャーナリスト〟が登場して〝警察〟との2大巨塔を築いたわけですが……当時も、推理小説のプロパガンダと謳われるアブ・ヴィッサー(Ab Visser/前述)のように既存推理小説のパロディを書いたり推理小説研究をしたりミステリに愛着を持っている方々もいらっしゃったとはいえ、〝探偵〟と同様に推理小説を専門で執筆する小説家いわゆる〝推理小説家〟も、根が下ろせない期間は長く、最近も他分野で成功した小説家が推理小説を描くということは少なくない印象です。
これを伝統の継続性が欠如していると表現することもできると同時に、他分野で培われた知識や経験が作品に生かされやすい環境でもあると思います。
まだまだ未読作品ばかりでわからないことばかりですが、オランダミステリは貴腐ワインのような佇まいをしていらっしゃるのかな、と下戸は考えております。お酒に詳しかったらカッコイイ例示ができただろうに……まあ、ひとまず、オランダミステリも面白いですからオランダ語を習得してくださいということが伝われば嬉しいです。
参考(いずれも最終閲覧は2025年10月18日)
・degitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel
・VN Detective en Thrillergids
P.S.
円安なので財布を慮って唯一、De gouden strop2025年受賞作『De prijs』を購入しました……俺は学術書やハードカバー評論を知っているから我慢できたけど乱読家だったら我慢できなかった……決め手は、著者ですね。
マルセル・ファン・デ・ヴェン(Marcel van de Ven/調査中)とウィレム・アスマン(Willem Asman/1959-)がタッグを組んで、De gouden strop史上初のコンビ作家への授与だそうです。
アスマン氏は2006年にデビュー作『De Cassandra Paradox』がDe gouden stropにノミネートされてからずっと推理小説執筆を続けてきてくださり、2018年にはRebound三部作の終幕『Exit』でDe gouden stropを獲得した方……そう、いわゆる「お、東野作品だ。おもしろそう」の感覚。(この感覚の正式名称って何ですか? わたしは「パブロフのベル発見」と呼んでいます)
ファン・デ・ヴェンは、長年オランダ警察特殊作戦部隊所属時代に潜入捜査官の経験を持っていたりテレビ番組オランダ版「Hunted」出演や起業していたり、おもしろい経歴をお持ちでいらっしゃるうえ、麻薬密売疑惑のある企業に潜入する警察官を主人公とした作品との相性は良さそう……。
まだ読み途中ですが、サスペンスフルで期待を超えてくれております。ありがとうございます。
以上!