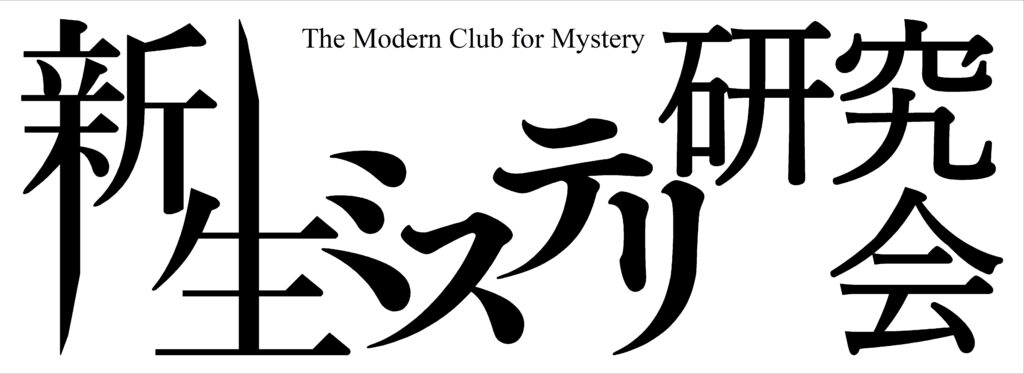
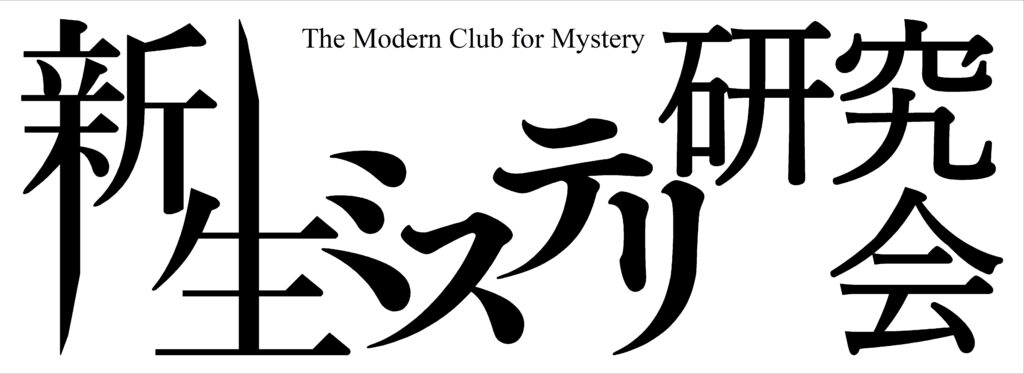
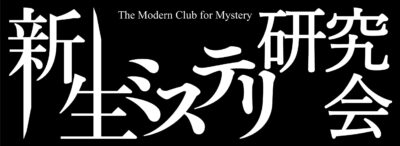
コラムを更新しました:『十戒』と『方舟』を比較してみる
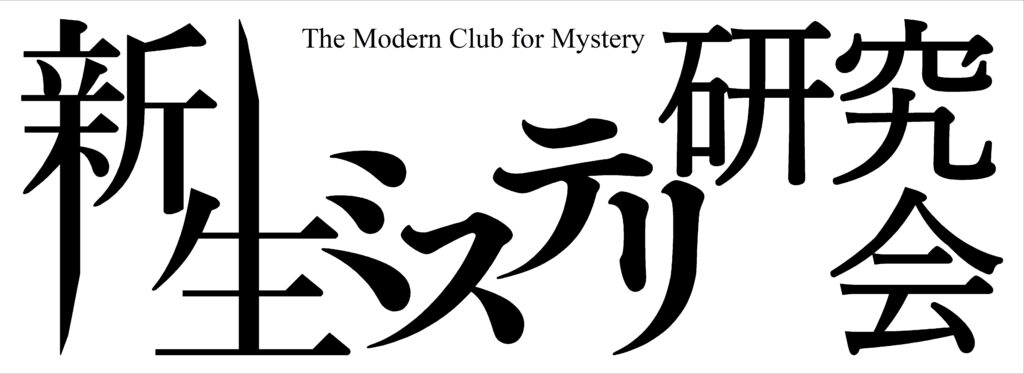
歴代文学フリマ記録
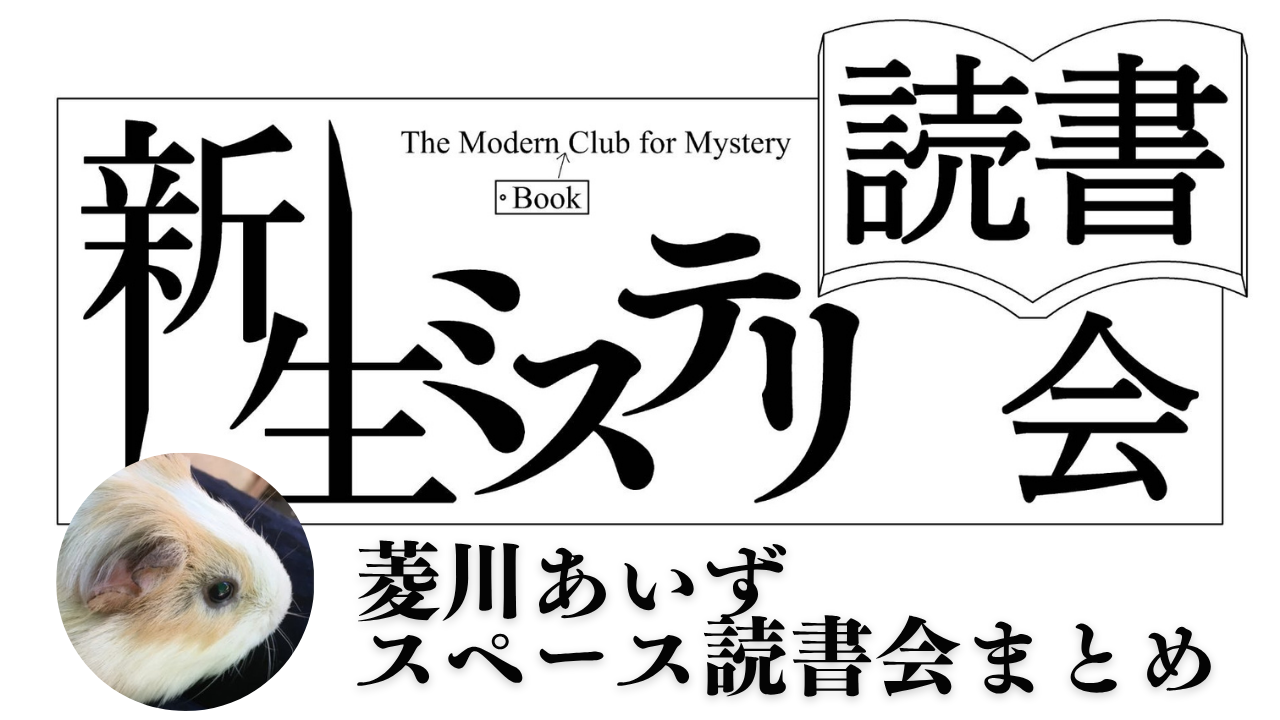
こんにちは。新生ミステリ研究会副会長の菱川あいずです。
もう半年以上前になりますが、前回、【『方舟』は本格ミステリのシンギュラリティか】というコラムを執筆させていただきました。
今回のコラムは、その続編ということで、『方舟』と同系譜の夕木春央の『十戒』をテーマに好き勝手に語りたいと思います。
なお、このコラムは『方舟』と『十戒』に関するエグいくらいのネタバレを含んでいますので、『方舟』と『十戒』をともに読んでいない方は、ここで立ち止まってお引き取りいただくようお願いします。
また、このコラムは執筆者目線での『方舟』と『十戒』との(大いにディティールを削ぎ落とした)構造分析であり、ハッキリ言うと、〈無粋〉です。このコラムを読んで、『方舟』や『十戒』の魅力を再発見していただくということはおそらくありません。
本来であれば、飲み会やスペース読書会でクダを巻いて話すべき内容を、僕個人が最近子育てで忙しくて、内に溜め込んでしまっているために、コラムという仰々しい形式となってしまっただけです。
ですので、『方舟』と『十戒』をすでに既読の方も、このコラムはなんか合わないな、なんかムカつくなと思ったら、すぐに引き返してください。
1 『十戒』は『方舟』の続編か
冒頭で『十戒』と『方舟』は〈同系譜〉と書かせていただきました。このようなハッキリしない表現をしたのは、ネタバレ防止のためです。ここを読んでいる方はすでに『十戒』を読んでいるはずなので、ハッキリ言うと、『十戒』は『方舟』の続編であると理解して良いと思います。
それは文庫版の後書きでも指摘されているとおり、『方舟』と『十戒』の犯人が同一=麻衣ちゃんだからです(それに伴って、当然ながら、世界線も共通します)。
探偵役が同じというのはシリーズものの定石ですが、犯人役が同じというのはなかなか珍しいパターンだと思いますが、『方舟』で最も魅力的であったキャラクターは麻衣ちゃんで間違いないので、妥当でしょう。
ところで、本コラムで語りたいのは、麻衣ちゃん愛ではありません。僕は麻衣ちゃんを愛してますし、ちゃん付けも決してやめませんが、このコラムではもう少し研究会らしい、建設的なことを語りたいと思っています。
このコラムでは語りたいこと――それは『十戒』は『方舟』の単なる続編にとどまらず、〈同系譜〉だということです。
2 『方舟』と『十戒』の共通点
なんだか話がグルグルと回っていて、混乱させてしまったかもしれませんが、ここから先は歯切れ良すぎるくらいに歯切れ良く書いていきますね。
『方舟』と『十戒』は、ハッキリ言って、似ています。それは単に雰囲気が似ている、とか、モチーフがともに旧約聖書だというだけの話ではありません。
両作品の〈構造〉が共通しているのです。
僕が両作の共通構造だと思っている点を以下に列挙します(ちなみに、共通構造はこれにとどまらないと思うのですが、ここで挙げるのは、僕が本コラムで論じたい部分です)。
① 特殊な条件によって組み立てられたクローズドサークル
② 土台からひっくり返すどんでん返し
③ 首を傾げたくなる証拠から導かれるフーダニット
④ 犯人の動機が〈生存欲求〉
『① 特殊な条件によって組み立てられたクローズドサークル』は、『方舟』では下から水が浸食してくる地下構造物(方舟)であり、『十戒』では犯人からの命令(十戒)によって脱出を禁じられた爆弾島のことです。
いずれも、単なる〈館〉や〈雪の山荘〉ではない、独特なクローズドサークルといえるでしょう。
この点は、それぞれの作品の個性となっています。また、読者に作品を手に取ってもらい、(多少無味乾燥した文章でも)続きを読ませる吸引力ともなっています。
『② 土台からひっくり返すどんでん返し』は、『方舟』が高く評価された点です。『方舟』では、一人だけを生贄に捧げれば良いというシチュエーションから、一人だけが助かり他は全員死ぬというシチュエーションへの転換があり、それに合わせて登場人物の生死、犯人の動機がひっくり返りました。
他方、『十戒』でも、大どんでん返しがあります。詳しくは別の章で後述しますが、簡単に言うと、探偵役による解決が実は〈フェイク〉であり、実際には探偵役こそが事件を仕組んだ犯人だった、というものです。
『③ 首を傾げたくなる証拠から導かれるフーダニット』というのは、どんでん返し前の〈フェイク推理〉(『方舟』に関していえばこの表現は不正確かもしれませんが……)の部分です。『方舟』でいうと、ウェス、(不必要に見える)首切り、爪切りといった一見すると〈?〉な証拠から犯人が特定されていきます。『十戒』だとこれは人為的に消された犯人の足跡です。
僕はこのフーダニット部分が(麻衣ちゃんほどではないですが)大好きです。両作品が単なる〈飛び道具〉として片付けられないのは、この〈いぶし銀〉なフーダニットのおかげなのではないか、という気がします。
『④ 犯人の動機が〈生存欲求〉』というのは、僕独自の着眼点かもしれないのですが、この点が僕は両作品の(下手すると最大の)魅力だと思っています。そして、この点が僕を始めとした麻衣ちゃんファンを全世界に生み出している要因なのではないかと思います。結局、全男子は、女の子の『お腹減った』に弱い、ということですね(もしくは『マクロス』の『生き残りたい』が刺さるというか……)。
少し真面目な方向に話を戻すと、『方舟』の犯人(麻衣ちゃん)の動機は〈唯一の生き残りになること〉であり、『十戒』の犯人(麻衣ちゃん)の動機は〈みんなで生き延びること〉なのだと理解できます。まさに〈生存欲求〉。『死にたくない』というただ一心で殺人を犯しているのです。これはこの上なく納得できる動機だと言って良いのではないでしょうか。
さて、ここで大事なことを言います。
僕は『方舟』と『十戒』に多くの〈共通構造〉
があることを、夕木春央先生から、ミステリファン(特に執筆者)に対する〈プレゼント〉だと思っています。
『方舟』は多くの読者に好意的に受け止められた作品であると同時に、執筆サイドにも大きな刺激を与えた作品だと思います。
もっと芯を食った言い方をすれば、『こんな作品を書きたい』と焚き付けた作品だと思います。
ただ、『書きたい』と思ったからといってそのとおり書けるわけではありません。真似したくても真似できないというのは、執筆に限らず、世の常です。
しかし、夕木春央先生は、『方舟』に引き続き、『十戒』を書くことによって、『方舟』に〈再現可能性〉を与えたのではないか、というのが僕の受け止めです。
別の言い方をすれば、『小説家になろう』の〈異世界転生テンプレート〉(トラックに轢かれて異世界転生し、ハーレムとチートを堪能する)と同様に、夕木春央先生はミステリにおける〈方舟テンプレート〉というものを生み出し、執筆サイドに提供してくれたのではないか、というのが僕の受け止めなのです。
3 『方舟』にあって『十戒』にないもの
よくよく考えてみるまでもなく、ある二つの小説を取り出して、その共通点を探るという行為は、失礼となりかねない行為です。『パクリだ』とか『コピーだ』という批判と捉えられかねません。
しかし、このコラムにおいて、あえて共通点を括り出した目的は、前述したとおり、〈方舟テンプレート〉の存在を見出すという点にあります。
ただ、それだけではありません。
共通点を括り出す作業は、同時に、相違点も浮き彫りにします。
僕が興味を持っている点は、まさに『方舟』と『十戒』との違いにあります。
この違いを記していくことは、共通点を括り出す以上にミステリを理解する糧になるだろうと信じ、まずは、『方舟』にあって『十戒』にないものを列挙してみます(無論、これは無限にあるので、僕が列挙するのは、僕が語りたいごくごく一部のみです)。
① 事件の外側でのどんでん返し
② ワイダニットのみのどんでん返し
『① 事件の外側でのどんでん返し』というのは『方舟』におけるどんでん返しである、一人だけを生贄に捧げれば良いというシチュエーションから、一人だけが助かり他は全員死ぬというシチュエーションへの転換というのは、殺人事件そのものには直接関連しないものである、というものです。事件への影響は〈動機〉の形成にとどまります(詳しくは後述します)。
この〈事件の外側でのどんでん返し〉が読者の意表を突いたのではないか、というのが、僕が考える、『方舟』の商業的成功要因の最たるものだと思っています。
多くの読者が無警戒であった大前提部分からひっくり返したということが、『方舟』を特別たらしめたのです。
『② ワイダニットのみのどんでん返し』を『方舟』が行っていたというのは、『十戒』と比較してはじめて際立つ点かもしれません。 どんでん返し前の推理も犯人は麻衣ちゃんでした。さらに殺害方法も、どんでん返し前とどんでん返し前で変わりません。
変わるのは、ただ、麻衣ちゃんが人を殺した〈動機〉だけなのです。
この〈動機〉の転換が、最後の〈カタストロフィ的展開〉に繋がるのが『方舟』の見事なところなのですが、従来のミステリの概念整理で言うと、『方舟』では〈動機〉=〈ワイダニット〉しかひっくり返していない、というのは重要な指摘だと思います。
上記の二つに加えて、③で『〈生存欲求〉を叶えるための唯一の手段としての殺人』を入れるか悩みました。
『方舟』と『十戒』を比べた時に、『方舟』の麻衣ちゃんの方が正当防衛感が強いというのは間違いないと思います。すなわち、『方舟』の麻衣ちゃんは、あの場面で殺人を犯していなければ自分が死んでいたといえるシチュエーションで殺人を犯していたのです。
他方、『十戒』では、ぼんやりと『ここまでしなくても……』という気がしてしまいます。人を殺さずとも生き残る手段は他にもあったのではないか、と。
しかし、これはあくまでも〈程度問題〉であって、もっといえば、〈各読者の感じ方の問題〉のような気がします。
それに、作中でそのような説明はされていないのですが、麻衣ちゃんはすでに『方舟』の時に人を殺しているので、『十戒』の時には人を殺すハードルが幾分か下がっていてもおかしくない、という気もします。
ゆえにこの点は、相違点として挙げるまでには至らず、雑感としてここに書き残すにとどめます。
4 『十戒』にあって『方舟』にないもの
ミステリ界隈において、『十戒』は『方舟』ほど称賛されていない、というのは、否定し難いところかと思います。
しかし、『十戒』は『方舟』の単なる〈劣化コピー〉などではありません。
『十戒』には、『方舟』にはなかった〈野心的な試み〉が加えられており、その部分の成否が『十戒』の真の価値を決するのだ、と僕は思います。
では、『十戒』の〈野心的な試み〉=『方舟』との相違点とは何なのか。二つ挙げてみます。
① フーダニットにまで及ぶどんでん返し
② 〈十戒〉を利用した叙述トリック
『① フーダニットにまで及ぶどんでん返し』というのは、『方舟』のどんでん返しがワイダニット部分に収まっていたことと好対照です。(『方舟』と違い、)『十戒』では、〈フェイク推理〉で指摘された犯人は麻衣ちゃんではありませんでした。どんでん返しによって、はじめて犯人が麻衣ちゃんであることが明かされるのです。
これは、極めて素朴な見方をすれば、『十戒』のどんでん返しの方が『方舟』のどんでん返しよりも〈派手〉だ、ということになるのだと思います。
しかし、おそらく多くの読者の感想はその逆で、『方舟』のどんでん返しの方が派手で、『十戒』のどんでん返しの方がこじんまりしている、と感じたのだろうと想像します。
その要因の一つは、前章の『方舟』のところで説明したことの裏面なのですが、『十戒』のどんでん返しは、事件の外側ではなく、事件の内側にある点です。『十戒』でひっくり返ったのは、事件の犯人であって、それはまさに事件そのものの反転に過ぎなかったのです(仮に『十戒』で事件の外側をひっくり返すのであれば、実は島にあったのは爆弾ではなかった、とかそういうレベル・レイヤーでの転換が必要だったでしょう)。
もう一つの要因は、犯人がひっくり返る(探偵役と犯人がひっくり返る)というのは、もはやミステリの〈王道〉であり、新鮮味がないということなのだと思います。みんながやっている〈派手〉なことより、誰もやっていない〈地味〉なことの方が目立つ、という逆説的なことが起こったのです。
そして、『② 〈十戒〉を利用した叙述トリック』については、コラムにおける長い独り言で済ませるべきではないくらいに、着目する必要があります。
蛇足かもしれませんが、まず前提として、『十戒』において叙述トリックが立派に使われていることを明らかにします。
〈叙述トリック〉の定義は多々あるとは思いますが、僕は、〈ヴァンダインの二十則〉を参考にし、
作中の登場人物ではなく、読者のみを騙すペテン
を叙述トリックと定義します。
『十戒』においては、作中の人物=主人公は、犯人が麻衣ちゃんだと知っています。
しかし、他方で、最終盤まで、読者は、犯人が麻衣ちゃんではないと騙されています。これは、主人公が、麻衣ちゃんが犯人であるという自己の認識を明かさないばかりか、麻衣ちゃんにはアリバイがあるという発言を主体的に行うからです。
叙述トリックを、
地の文が嘘を吐く
と単純に定義する立場もあるとは思いますが、まさに本作では、地の文=主人公視点が、麻衣ちゃんが犯人ではないかのような振る舞いをすることによって、嘘を吐いているのです。
ということで、『十戒』が叙述トリックを用いていて、このことがこの作品の特徴であり、武器であることは間違いないと思うのですが、問題とすべきなのは、果たして『十戒』の叙述トリックは成功しているのかどうかです。
『十戒』の叙述トリックが成功しているという立場だと、その成功の秘訣を以下のように説明するのだと思います。
主人公が、麻衣ちゃんが犯人ではないかのような振る舞いをしたのは、アンフェアではない。なぜなら、主人公は、〈十戒〉によって、〈犯人を探してはならない〉という強迫観念に縛られていたからだ
ここではまさに〈十戒〉の機能が強調されるわけなのですが、僕は、申し訳ありませんが、この見解には立てず、『十戒』の叙述トリックは腑に落ちていません。
それはなぜかというと、たしかに主人公は〈十戒〉に縛られていたけれども、それは対外的な制約であり、内心まで制約するものではないと考えるからです。
抽象的に書くと分かりにくいかもしれませんが、もう少し分かりやすく言うと、「犯人は麻衣ちゃんだな」という〈心の声〉を主人公が漏らさないことは不自然だろう、という指摘です。〈十戒〉の制約により、主人公は、「犯人は麻衣ちゃん」ということを口が裂けても言えません。しかし、心の中では「犯人は麻衣ちゃん」と思っているはずで、その〈心の声〉を読者に開示しないのはアンフェアなのではないかと思うのです。
このことをアンフェアと思うかどうかは、読者のこれまでの経験や感受性次第なのかもしれませんので、あくまでも個人の感想です。
もしもこのことをアンフェアと感じない方がいれば、おそらく『十戒』を高評価し、もしかすると、『方舟』よりも上位に置くのかもしれません。
さて、ここでこのコラムを終わらせても良いのかもしれませんが、残念ながら、僕は東野圭吾作品に魅せられてミステリ界隈に組み込まれた人間ですので、叙述トリックには一過言以上持っています。
そこで無粋中の無粋を承知で、『こうすればアンフェアを回避できたのではないか』という提案をしてみます。
【提案】
『私は見てはいけないものを見てしまった』と地の文で書く
人間が行動に至るまでのフローは、
認知→判断→行動
で成り立っています(僕は今訳あって自動車教習所に通ってますが、その教科書の序盤にもそう書いてあります)。
『十戒』の叙述トリックをアンフェアに感じるのは、主人公が、麻衣ちゃんの不審な行動を〈認知〉しているのに、そのことを黙っている点だと僕は思います。〈十戒〉における〈犯人を探してはならない〉という掟は、〈判断〉=〈誰が犯人だろうかと推理する〉、や、〈行動〉=〈犯人は○○だと指弾する〉ということを妨げても、その前提となる〈認知〉=〈麻衣ちゃんが不審な動きをしている〉を知覚することは妨げないはずです。ゆえに、この部分を完全に省いて地の文を書くということは、とても恣意的に思えます。
この誹りを回避するためには、地の文に書けば良いということになります。
ただし、『麻衣ちゃんが夜に抜け出していた』と率直に書いてしまうと、台無しです。
そこで『私は見てはいけないものを見てしまった』くらいの叙述にとどめます(これ以上深入りしなくて良いのは、〈十戒〉がその後の〈判断〉、〈行動〉を制約しているからです)。
ただ、これを書くと、勘の良い読者は、『見てはいけないもの』=〈麻衣ちゃんの不審な行動〉と気付いてしまいます。
そこで〈読者を積極的に真相から遠ざける仕掛け〉をここに入れます。たとえば、その夜、主人公は、麻衣ちゃんではない別の人物Aを尾行した後、寝室に戻り、麻衣ちゃんと同室で寝た、というストーリーにします。すると、主人公の『見てはいけないもの』とは、別の人物Aのことであり、麻衣ちゃんのことではない、と誤導できます。
この仕掛けは、某山荘の叙述トリックのアレンジです(なお、東野圭吾作品ではないです)。
この私見は、あくまでも一つの見解に過ぎません。この見解が、論理的に、商業的に正しいのかは不明ですが、考えたことをそのまま開示させていただきました。