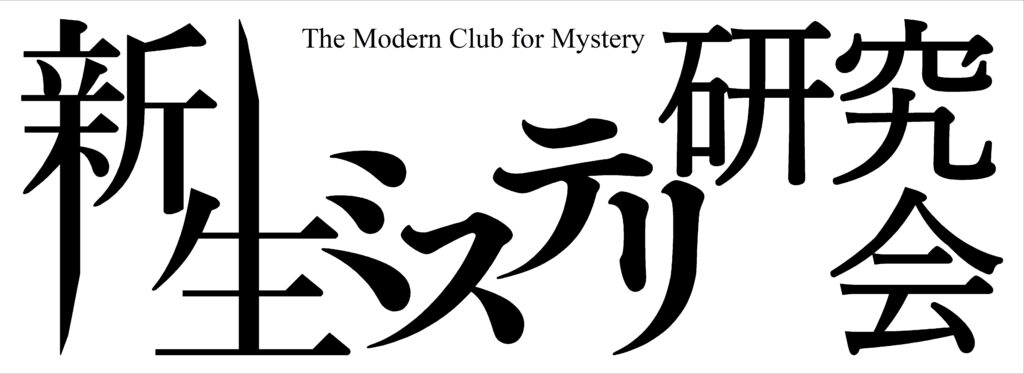
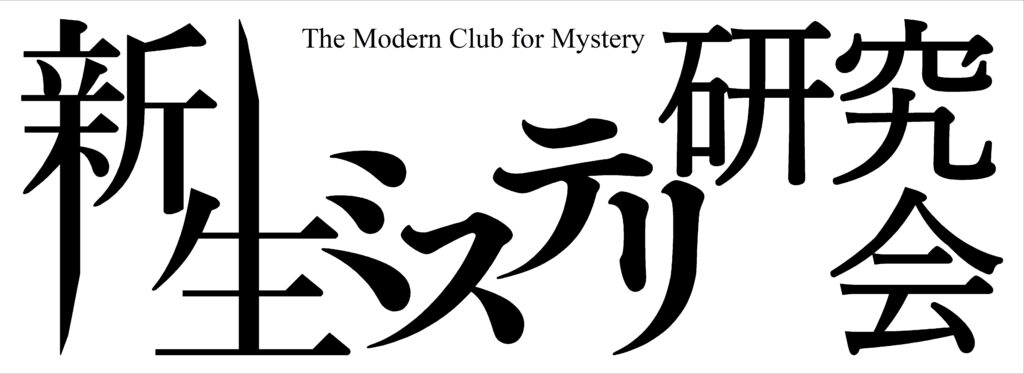
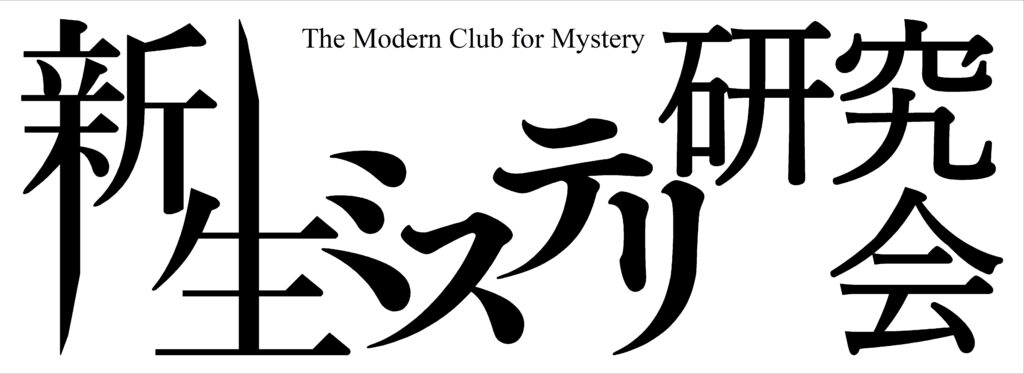
25/05/11 文学フリマ東京40
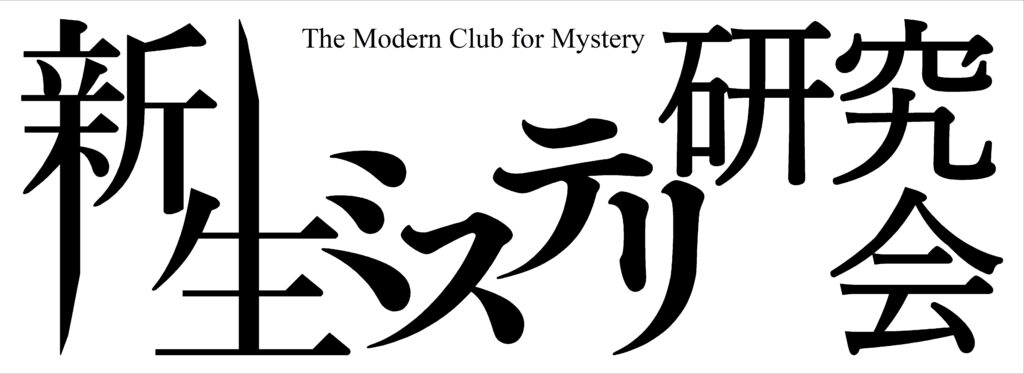
文学フリマ東京40に出展します
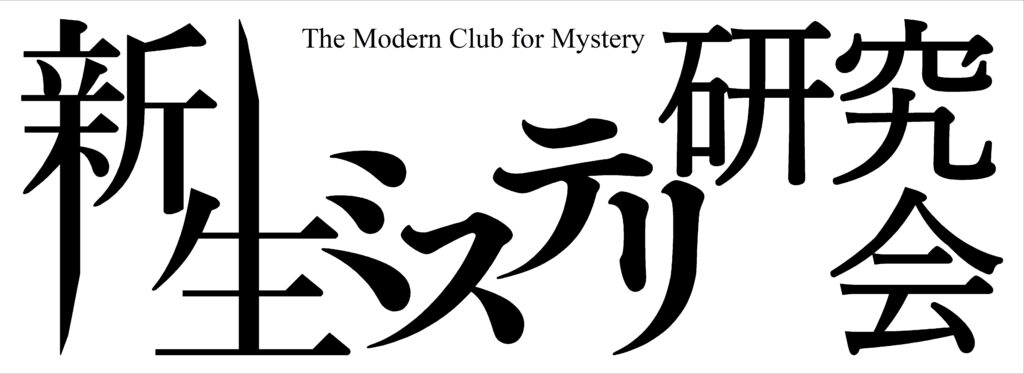
凛野です。
私事で恐縮ですが、この度、第24回「このミステリーがすごい!」大賞にて、私の応募作『名探偵・桜野美海子と天国と地獄』を最終候補作に選んでいただきました。有難いことです。思えば、自作を初めて新人賞に応募したときには15歳でした。挑戦を続けてもう15年になります。今度こそプロになりたいですけれど、こればかりはどうなるか判りません。
最終候補に残ったからと云って、著者にできることはありません。小説の新人賞において、選考を進んでいくのは著者ではなく作品です。それははじめに応募した段階で、著者の手を離れています。よって、現在の私が何をしているかと云えば、相変わらず、小説を書いています。
私が偉そうに云うことでもないですが。この時代、小説家と云っても、その活動の幅は様々に広がっています。しかし結局のところ、小説家というのは小説を書く。それが第一であることは変わらないと思います。正確には、変わらないでほしいと思います。
小説を書いていると、その小説にとって、その時々の自分に足りないものが見えてきます。もっとこういう読書をした方がいいとか、こういう知識を得た方がいいとか、こういう経験を積んだ方がいいとか、単純に筆力が足りていないとか、テーマに対する理解が浅いとか、環境面や精神面で何か執筆に集中できない要因があるとか、まあ色々。そこから、その小説を書いていくために必要なアクションが決まっていきます。
このように、小説を書くというのは、小説を書く行為だけでなく、そこから要請される種々のアクションまで含む営みであると、私は思います。小説家の活動もまた、そういう順序で決まっていくのが自然であり、本来的と云えるのではないでしょうか。
そうやって出来上がった作品が、たとえば新人賞を受賞しプロとなったり、売れてシリーズ化したり等、自分をまた新しい場所に連れていってくれることが理想です。何をするにも、まずは作品ありき、ということですね。
ところで、〈才能〉という言葉を厳密に扱おうとすると、どうしても話が複雑になるのですが、ここでは単純に扱わせてください。世間一般に、あまり苦労せずに成功することを『才能がある』と表現する場合があります。それで云うと、私は明らかに才能がない人間です。
ある分野で成功するには約1万時間の努力が必要だ――という〈1万時間の法則〉なんて言葉もありますけれど、私はとっくに1万時間以上を小説の執筆に費やし、まだプロになれていません。そもそもプロになるのはまったくゴールではなくて、プロになってからが厳しい世界です。「きみには才能がないんだから諦めなさい」と何度も云われてきましたし、実際に諦めてしまう人達を何人も見てきました。
それでも、私はずっと続けています。小説を書きたい。書き続けたい。プロを目指しているのは、より多くの人々に小説を読んでいただきたいからです。書かれた小説は、読まれる必要があります。小説の価値はそこにあります。様々な分野でプロとアマチュアの垣根が曖昧となっている現代ですけれど、小説家にとっては、発行、流通、宣伝と、あらゆる側面において、商業出版はなお有効な手段でしょう。
ただし、それは手段であって、目的ではありません。小説家の第一は小説を書くこと。何をするにも、まずは作品ありき。愚直と映るかも知れないですが、私にはそういう考え方が合っているようです。ゆえに、諦めるという発想がないのでしょう。もしも私がプロの小説家となることを目的と捉えていたなら、自分に才能がないと判った時点で心折れて、ここまで続いていないと思います。「プロになりたい」というモチベーションにとって、才能は重要です。しかし「小説を書きたい」というモチベーションには無関係です。
もっとも、人生は有限であり、そのうえ何が起きるか判りません。もしかしたら小説を書けない身体になってしまうかも知れない。小説を書けるというのがどれだけ恵まれたことか、しっかりと認識しながら、自分にできることを精一杯やっていく。結論、これに尽きますね。
ということで、最後に宣伝。これも自分にできることのひとつです。
9月14日(日)の文学フリマ大阪13に「新生ミステリ研究会」(お-59~60)も出店します。私も参加し、既刊に加えて新刊『マイス・メガロマニアック』を販売予定です。ブースでは無料配布の短編もご用意していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りくださいませ。お待ちしております。
以上